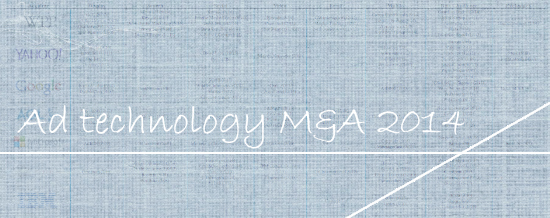「State of AdOps」は、現在急速に伸びている運用型広告の成長を支え、実際の現場で価値をつくりだしている広告運用(AdOps)のスペシャリストたちに焦点を当てるインタビューシリーズです。広告運用の最前線にいる方々が感じていることを語って頂くことで、運用型広告の輪郭を少しでも捉えることができればと考えています。
※過去の記事は
こちらから。
第14回目は、専門家によるコンテンツが充実し、歴史あるメディアである All About を運営されていると同時に、アドテクノロジーへも積極的に取り組んでいらっしゃる株式会社オールアバウトで広告運用周り全般をマネジメントされている小林秀次(こばやし しゅうじ)さんに、メディアとしての広告運用やマネタイズの現状について、忌憚のないお話をお聞きしました。
# インタビューは 2014年10月某日に行われました。
ちゃんとした情報を、手間を掛けて発信し続ける。
●まずは、小林さんが現在のお仕事に就かれるまでの経緯と具体的な業務内容を教えて下さい。オールアバウトの小林です。専門家による総合情報サイト All About で広告収益となる商品企画全般を担当しています。
オールアバウトに入社する以前は、インターネットでもメディアでもない、通販企業で雑誌編集の仕事をしていました。取材、撮影、台割、コピーライティングなど、商品を魅力的に見せるという仕事を通じて、編集としてのキャリアを積んできました。
2004年頃になって、通販もインターネットだという流れになり、雑誌だけでなく自社サイトや楽天市場、ヤフーショッピング等に出店するようになりました。私もそれまでの商品コピーを書く仕事から、その売上を伸ばしていくためのメールマガジンやアフィリエイト、SEO、リスティング広告など、徐々に集客や販売促進の仕事を担当するようになりました。
当時担当していた商品が単価の高い「こだわり系グッズ」だったのですが、その商品を対象とした広告出稿で、All About が最も高いコンバージョン率だったことが分かりました。元々は代理店がメディアプランに入れていた程度だったのですが、その結果を知って All About というメディアに興味を持ちました。「メディアが面白いんじゃないか?」と思ったんですね。
●そこから「じゃあ転職しよう」というのがすごいですね。ECサイトをやっていると、インターネットは様々な数字が見られることを肌で感じることができます。インターネットにはメディアも情報もどんどん溢れるようになる中で、All About は人(専門家)にファンがついているアナログっぽいメディアでした。広告出稿して効果が高かったのも、情報の信用度が高かったからです。ちゃんとした情報を、手間を掛けて発信し続ける姿勢は、情報が爆発する時代だからこそ価値を出し続けられるに違いない。そう思って転職を決意しました。
2006年に転職し、当初は All About が新規事業として運営していたECサイトを任され、5年ほど担当していました。その後、元々メディアで働きたくて転職したこともあって、ECサイトが分社化された2011年に All About のメディア事業部へ異動し、広告周りを見るようになりました。そこで最初に担当したのが運用型広告です。
メディアにとっての運用型広告は、純広告ではない空き在庫をマネタイズする仕事という意味で、当時はYahoo! アドネットワーク(現YDN)さん、マイクロアドさん、Advertising.comさんなど、アドネットワークを活用して純広告以外の枠をいかにマネタイズするかを試行錯誤していました。現在では、純広告、タイアップ型広告など、広告収益がある商品企画全般を担当しています。
●かなり幅広い分野を担当されていますね。自分の部署の仕事を言い換えれば、広告営業担当のための武器を作る武器屋だと思っています。
武器屋はただ武器を店頭に並べていればOKではなく、武器の価値を伝えないと使い方が分かりませんし、買ってもらえません。武器の種類を揃えるだけでなく、特徴をしっかり伝えることが大事だと思っています。
メディアの広告運用には専任の担当者を。
●オールアバウトさんというと、伝統的メディアであると同時にアドテクノロジーへも非常に注力されている印象があります。メディア側での運用型広告のお取り組みについて、具体的にどのようなことをされているのか教えて下さい。まず、空き在庫のマネタイズは運用の要素がかなり高いです。そういう意味で運用型広告だと思っています。
我々メディアサイドは、一つのネットワークやエクスチェンジを入れて放置しているわけではないんです。例えば、Googleさん(AdSense / DoubleClick Ad Exchange)を採用したとします。「Google を一度入れてしまえばあとは RTB で勝手にオークションしてくれるからそのままでいい」となるのではなく、データを見ながら毎週・毎日のように運用が発生していきます。
運用とは、データを見ながらフロアプライスを調整したり、タグを呼び出す順番を変えたりするようなことを指します。他にも、RTB に広告在庫を出す前に、ある事業者との固定取引を優先的にオークションし、そのフィラーとして Google を出す、といったようなことです。
これはあくまで単純な例ですが、実際には複数社のネットワークを組み合わせ、All About 内に存在する広告枠ごとに個別に分析し、設定を繰り返して収益の最大化を目指していきますので、かなり複雑な作業です。デマンドサイドから見れば鏡の表裏になるわけですが、業務自体はまさに広告運用と言えるのではないでしょうか。
●非常に興味深いです。ちなみに複数のネットワークを枠ごとに運用していくのは、片手間ではとても難しいのではとお察ししますが、実際に組織としてはどのように対応されているのでしょうか?以前は固定単価のネットワークが多かったのでシンプルでしたが、現在は日々数字が変わるモデルですので、片手間ではとても無理です。収益に直結する大事な業務なので、専門の担当者がおります。
また、以前のようにネットワーク事業者の担当者とやりとりするだけでよかった時代から、ネットワークの先の DSP などのプレイヤーから直接連絡がくるようになったのも、担当者が必要になった要因の一つです。
例えば、「ある特定のセグメントのインプレッションを確保したいので、個別のタグを導入できないか?」といった問い合わせは、専門の担当者でないと対応できません。純広告に近い考え方の「プログラマティックプレミアム」というモデルが伸びると言われている中で、RTB を通じて買い付ける DSP の動きが活発なため、通常の広告代理店の商流には乗らない取引も増えてきているような印象です。
●なるほど。デマンド側の広告運用からすると、「このドメイン」「このプレースメント(枠)」という指定で買いに行くというよりは、ターゲティング配信した結果を分析していく過程で、よいドメインやよい枠を事後的に「発見」する、というのが感覚として近いのですが、DSP はメディア指定で買い付ける要望が強いということなんでしょうか? 仰るとおり、広告主さんは必ずしも「All About の枠が買いたい」と思っているわけではないと思います。また、ドメイン指定の場合は、「買いに行く」というより「除外する」用途として使われることの方が多いですよね。
一方で、DSP の事業者からすると、需給バランスの問題もあると思いますが、どのメディアの結果が良かったのか把握できる立場にあるので、予約型のようなかたちで特定の広告在庫を抑えたいというご要望が発生するようです。「このセグメントにはこのインプレッションが効果がよい」ということが分かれば、多少単価が高くなってもそれ以上の効果を広告主にお返しできますから。
メディアからしても、もし需要があれば優先的に在庫を抑えることでインプレッションの単価も高くなりますので、収益にもポジティブに作用します。取引形態によってインプレッションの価値が変わることになりますので、やはり専任の担当者は必要ですね。枠を放置することは今のメディア運営ではできません。
テクノロジーが進んでいるからこそ、人が大事です。
●ありがとうございます。次の質問ですが、こういったメディアサイドの広告運用を考える上で、次に発生する問題はブランドとボリュームのバランスではないかと思います。このあたりの調整も専任の方がやられるのですか?広告のボリュームを加味するのは非常に大事です。細かな個別対応をし過ぎるとタグが増えすぎてしまってサイトパフォーマンスにも影響しますし、社内的にもリソースもかかってしまいます。
そのため、プログラマティックプレミアムのような取り組みの場合は、僭越ながら最低限のラインは設けさせて頂いています。呼び出しの順序なども、経営的な側面を考慮しているのは事実ですし、メディアからすればほぼ純広告なので、配信の審査基準もほぼ純広告と同じだと考えています。
●お話をお聞きしていると、そういった特別な対応ができる DSP はおのずと限られてくるのでは、と思ったのですが。はい、限られてきますね。DSP さんやアドネットワークさんなど、一緒に新しい取り組み、面白い取組みができる企業さんとやり取りすることが増えてきています。
●一口にメディアの広告運用と言っても、カバーする範囲が実に広い印象です。プライベートディールのようなアライアンスに近いような仕事もあれば、配信面ごとのタグの順序やフロアプライスの変更など、仕事は多いです。
同じ媒体でも配信面によって結果が大幅に違うということはよくありますし、案件との相性も違います。
また、ある時期に特定の SSP の結果がすごく良かったとしても、単発的に案件が集中しただけかもしれませんし、翌期も同じように結果がよいとは限りません。
短い期間の結果だけを見て SSP やネットワークの判断をすることは、利用するプラットフォームをコロコロ変えることに繋がるため、メディアの運用が安定しなくなり、収益向上のヒントも見つかりにくくなります。SSP やネットワークとしても安心して取引できなくなるデメリットもあります。
そのため、収益性の差異がそれほど大きくなければ、頻繁にスイッチングせず、ご担当者としっかり付き合える企業を選択するよう心がけています。SSP やアドネットワークは、接続している DSP の数で差別化することはもう難しいと思いますので、一緒にパートナーとしてどこまで真摯に向き合えるかが大事ですね。
デマンド側と同じように、メディアの広告枠も PDCA を回していく必要があります。SSP などのメディア側のプラットフォームが安定していれば、デマンド側との相性を確かめたり、昨対での比較もできるようになりますし、協力して新しい取り組みを行うこともできるようになります。対応が場当たり的にならないためには、同じ未来が描ける事業者さんと長くお付き合いすることが大事です。
●メディアの広告運用の最終目的は RPM を上げることだと思うのですが、事業者とお付き合いする上で、RPM 以外に気にかけていることはありますか?メディアの運用型広告の売上は RPM×インプレッション数 ですので、RPM 以外で挙げるとすれば、広告在庫の拡大に寄与する活動です。
メディア側は出稿された結果は分かりますが、出稿前に広告主側にどのようなニーズや傾向があるのかは極端に言えば知ることができません。逆に、デマンド側のニーズが分かれば、我々メディアとしてはニーズに合ったコンテンツを作り上げることができます。
事業者の方々と情報共有することで、「A という分野の反応が良かったから、もう少し A に関連するテーマの記事を厚くしようか」といった企画につなげることができます。
データを活用した新しい広告メニュー
●メディアとデータの関係についてお伺いします。メディアにとってのデータは、昨今の DMP の盛り上がりや、パブリッシャートレーディングデスクのようなデータドリブンの新たな取り組みにフォーカスが当たるようになって、以前にも増して重要性を増しているように思います。その辺り、オールアバウトさんはどのように取り組んでいらっしゃるのか、可能な範囲でお聞かせ願えれば。データ活用に向けて具体的に取り組んでいる事例を申し上げますと、
『All About ユーザーディスカバリータイアップ』という広告メニューをフリークアウトさんと共同で展開しています。
『All About ユーザーディスカバリータイアップ』
adinfo.allabout.co.jp/download/editorial/userdiscovery.pdf(PDF)このメニューをかんたんに説明しますと、All About はたくさんのカテゴリに分かれており、どのカテゴリを閲覧したかというデータを持っています。このデータと、広告主さんの持つ訪問データを突き合わせて、既存ユーザーの含有率が高いカテゴリを選出します。
既存の含有率が高いカテゴリは潜在ユーザーも多いということになるので、選出されたカテゴリに対して、まだタイアップページに訪問していないユーザーはタイアップ記事へ誘導し、既にタイアップへの訪問履歴があるユーザーは広告主のサイトへ直接誘導する、というメニューです。
※adinfo.allabout.co.jp/download/editorial/userdiscovery.pdfより抜粋これは、閲覧データをそのままターゲティングに使うのではなく、広告の商品企画に活かしていこうという試みです。
以前は「All Aboutのデータを使いたい」というニーズが多かったですが、単なるデータの提供はビジネスとして成立しません。取引として大きくなりにくいという理由もありますが、単にデータサプライヤーとして提供したのでは、我々にとって非常に大事なデータがその後どう使われているのか分からないからです。
●この『ユーザーディスカバリータイアップ』は、ある意味パブリッシャートレーディングデスクと言えるような取り組みですよね? そうですね。パブリッシャートレーディングデスクというとメディアが自社でデマンド側の広告運用もすべて担うというイメージですが、オールアバウトですべて賄う必要はないと思っていますし、トレーディングデスクとして他社と比肩できるようなノウハウやリソースがあるわけでもありません。
こういったデータを活用した新しい商品開発を行なっていく上で、信頼できるパートナーとしてフリークアウトさんがいらっしゃったのが、この商品が世に出せた理由でもあると思います。ちなみに、この商品を実際に運用してくれているのは、
以前このインタビューにも登場した時吉さんです。
●やはり、運用型だからこそ人が大事ということですね。広告運用は横展開がしにくいですよね
●広告運用というお仕事、続けてこられてどのように感じていらっしゃいますか?運用が発生するネット広告メニューはすべてそうですが、やったらやっただけ結果が出て、それが目に見えることがやはり楽しいですね。
以前は通販の仕事をしていましたが、売上という結果はもちろん分かるものの、コピーが良かったのか、写真が良かったのか、タイミングがよかったのかといった売上に繋がった要素を分析することができませんでした。デジタルはそれが分かります。
分かったからといって毎回結果が出るとは限りませんが、何かしらの知見は必ず得られます。知見が得られれば次にするべきことが見つかりますから。
一方で、絶対のセオリーがないことが課題と言えば課題でしょうか。ネット広告は変化がとにかく早い分野ですし、シンプルに横展開できないことが多いです。商品が変われば使うチャネルも結果も変わりますし、ある商品は A という DSP ではいい結果だったけど、B の DSP ではあまり振るわない、ということが頻繁に起こります。アルゴリズムが少し変わっただけで、結果は大きく変わってしまいますしね。
●でも周りからは「横展開しなきゃ」って言われますよね。言われますね(笑)。
基本となる考え方や、PDCA を回すワークフローは横展開すべきです。ただ、知見や事例がそのまま別のキャンペーンに適用できるかというと、普通それはできません。素材やメニューに合わせて適切な調理方法が選択できるのが運用の価値だと思いますので。
横展開の圧力が強いのは、「運用=オートメーション」と勘違いされているケースが多いことが原因かもしれません。「どうせ空き枠だから自動化しなよ」という扱いを受けることも実際はありますし(笑)。ただ、そこに力を入れるだけ入れられれば得られる情報は増えますし、収益性も上がっていきます。運用がマネタイズにとって重要だということを周りからもっと理解を得られるように、努力を続けていかないといけないと思っています。
インベントリを生み出すことができるのがメディア
●得られる情報が増える、というお話がありましたが、やはり運用とデータは不可分の関係にあると思います。メディアの運用でデータ活用などは進んできていますか? まさに、これまではメディアが自社のユーザーを把握する方法はアンケートやサンプリングデータが主流でした。最近 DMP が本格的に利用できるようになって、アクセスの全数から類推ができるようになりました。
DMP の導入によって情報の精度が上がりましたので、運用にフィードバックできる情報が増えています。例えば、「データを見ながらユーザーが求めていることを今まで以上に把握した上でコンテンツが作れる」でしたり、「収益性の高いジャンルのコンテンツ作成に力を入れる」といったことができるようになりました。
一次情報をつくり出すのがメディアですから、広告運用の文脈で言い換えれば
インベントリを生み出すことができるのがメディアです。トレンドに振り回される必要はありませんが、最新の情報やデータをうまく運用に取り入れ、オールアバウトの色に染めていくことで、メディアの価値を上げていくことができると考えています。
●素晴らしいですね。本当はこの流れでキュレーションメディアとかネイティブ広告の話も聞きたいですが、それはまた別の機会に…(笑)。最後に、小林さんから見た運用型広告の展望などがお聞きできればと。私見ですが、3つの方向性があると思っています。
1つは、
より一層のプライベート化です。これは、プログラマティックプレミアムのようなプライベートディールが増えるという意味ではなく、デマンドサイドの広告運用者とメディアが今まで以上に密接に連携していくことで、データの共有、精度を上げていく施策ができるという意味です。
データを活用してターゲティングを今より一層細かくしていこうという意味ではなく、デマンド、サプライ双方にとって有益なクラスタリング(分類)を作ったり、その精度を上げていくことができるのではないかと考えています。全体がそうなっていくというよりは、一部で先進的な取り組みが進んでいくといった流れをイメージしています。
2つ目は、展望というより希望ですが、
メディア側のアドテクノロジーに関する取り組みを発信する機会を増やしていきたいと思っています。アドテクノロジーはデマンド側の情報こそたくさんありますが、メディア側はベールに包まれていると言いますか、情報がなかなか出てこないことが多いです。
もちろん、ソーシャルやキュレーションというジャンルでのメディアは事例や情報が出ていますが、我々のような一次情報の発信を行なっているメディアからはなかなか情報が出ていないため、実際にはそうではないにも関わらず、取り組みが遅れているという評価になりがちです。オールドメディアと揶揄されたりもしています。
オールドメディアからの発信が増えた結果、何がどう変わるかは正直分かりませんが、少なくとも情報の非対称性は解消していきたいと思っています。メディア側が遅れているという評価が変わることで、先進的な取り組みも徐々に増えていくのではないかと、そのように考えています。
最後3つ目は、
情報を出すだけでなく、繋げる機会を増やしていきたいということでしょうか。個別の情報交換だけでは取り組みは拡がりませんし、一方的な情報発信だけでも不十分です。デマンド側はオフラインのイベントや会合が頻繁に開催されていると思いますが、その場にメディアがいることは必ずしも多くありません。
一人や一社でできることは限られていますので、様々なプレイヤーが繋がることで、メディア側の広告運用にも「場」ができるのではないかと考えています。みんなで盛り上げていきたいですね。
●本日は貴重なお話、ありがとうございました!All About(オールアバウト)


















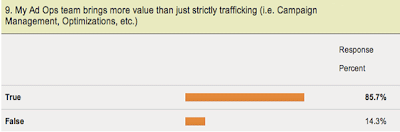
































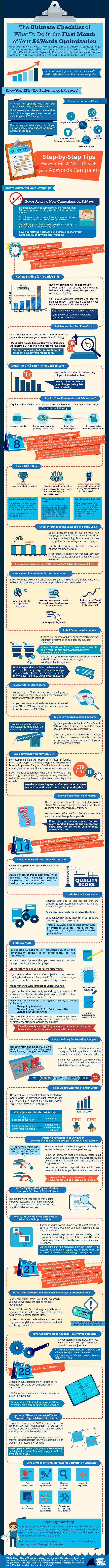 >The Ultimate Checklist on How to Optimize Your Google AdWords Campaign in the First Month – An infographic by the team at
>The Ultimate Checklist on How to Optimize Your Google AdWords Campaign in the First Month – An infographic by the team at